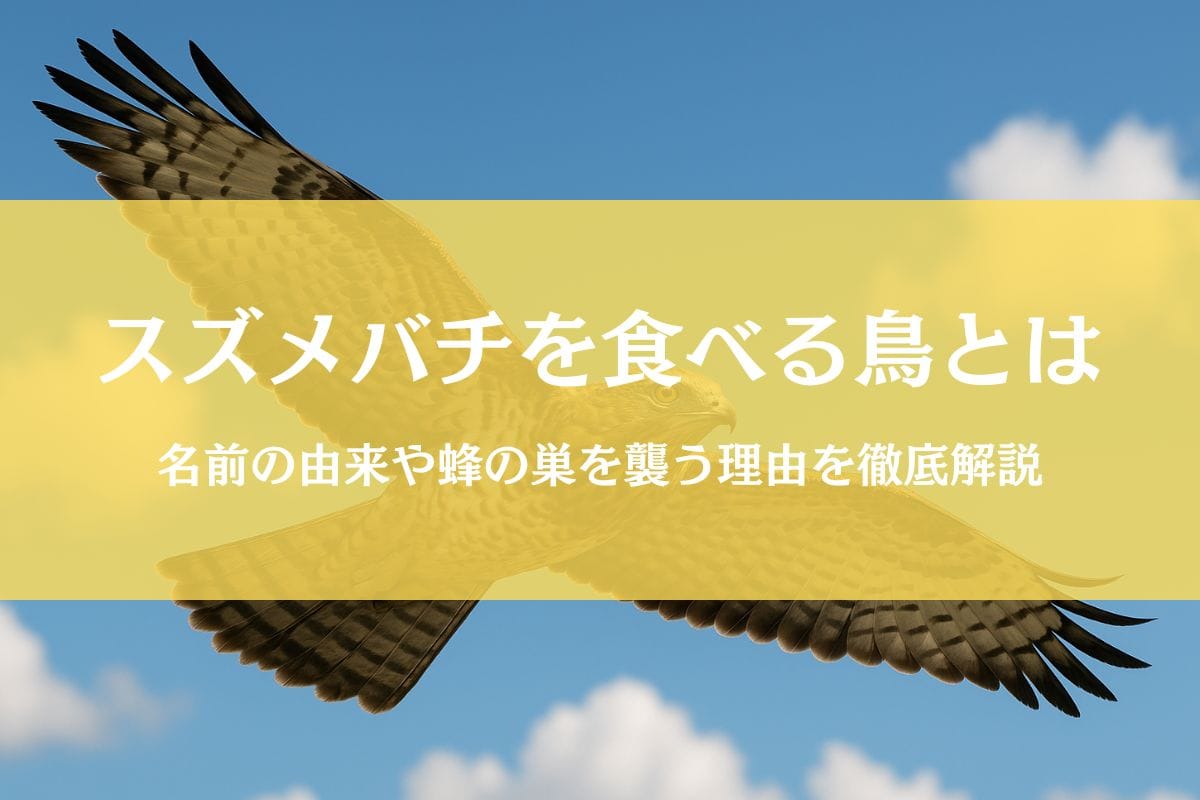空を舞うタカの中でも、スズメバチを食べるという驚くべき生態を持つのが「ハチクマ」です。
毒針を持つスズメバチを恐れるどころか、巣ごと襲って幼虫やさなぎを食べてしまうという大胆さ。その一方で、実は日本では準絶滅危惧種に指定されるほど貴重な存在でもあります。
「なぜ刺されないの?」「どこで見られるの?」「飼育はできるの?」といった疑問も、読めばスッキリ解消。さらにクマタカやカラスといった、他の鳥との関係・生態の奥深さにも迫ります。

自然界の天敵関係や、進化の妙を感じられる内容になっています。スズメバチの敵ハチクマのすべてを、ぜひ最後までお楽しみください。
この記事のポイント
- スズメバチを食べる鳥「ハチクマ」の特徴
- ハチクマがスズメバチに刺されない驚きの理由
- クマタカなど他の猛禽類との違いと見分け方
- 絶滅危惧の現状や、人間ができる保護のかたち
スズメバチを食べるのに刺されない!天敵ハチクマの大きさや生息地はどこ?

- 大きさや特徴
- 生息地はどこ?
- 名前の由来
- ハチクマの鳴き声
- 刺されないのは羽根のおかげ?
- 蜂の巣を襲う理由
- メスとオスの見分け方
大きさや特徴

ハチクマはタカ目タカ科に属する大型の猛禽類(もうきんるい)。全長はオスで約57cm・メスで約61cmほどあり、翼を広げると135cm前後にも達します。メスの方がわずかに大きく、身近な猛禽であるトビより少し小さいくらいの体格です。
体色には個体差が大きく、背中は黒褐色・腹部は淡い褐色の羽毛をもつものが多数。ただし中には全体に白っぽい個体や濃い褐色の個体もいて、一羽ごとに模様が異なります。翼の下面には、黒褐色の横縞模様が入る傾向があります。
さらに、ハチクマの顔や首まわりには小さく硬い羽毛がびっしりと重なって生えており、まるで鎧のように密集しています。この羽毛のおかげで毒針を持つハチに立ち向かっても刺されにくい構造になっているのです(詳しくは後述します)。

こうした点から、ハチクマは「スズメバチの天敵」とも称されるユニークなタカと言われるのです。
生息地はどこ?

ハチクマは主にユーラシア大陸東部に広く分布する渡り鳥で、日本には夏鳥として飛来します。毎年5月頃になると東南アジア方面から繁殖のために日本各地(主に九州以北)へやって来て、低山帯の森林に棲みつきます。
広葉樹や針葉樹が混ざる山間の森を好み、大木の枝が分かれた高所に巣を作って繁殖。実際に北海道・本州・四国・九州の山地でハチクマの営巣・繁殖が確認されています。
秋が近づくと繁殖地から旅立ち、9~10月頃には東南アジア方面の越冬地へ向けて南へ渡っていきます。その移動距離は往路で1万km以上にもなるとされ、はるか中国大陸を経由して東南アジアまで長旅をすることがわかっています。

こうした季節移動(渡り)の習性があるため、ハチクマは日本では夏にしか見られません。私も昨年9月、長野県の白樺峠という渡り鳥の観察地でハチクマの群れを目にしました。
ちょうど十数羽ものハチクマが、上空を旋回しながら南へ飛び去っていく光景は壮観の一言。スズメバチが気になる害虫マニア(の私)にとっては、胸が高鳴る瞬間でした。ハチクマが飛び交う里山の秋空は、まさに「大空を舞う謎のハンター」という表現がぴったりの光景なのです。
こうした理由からハチクマは現在、日本のレッドリストで準絶滅危惧種に指定されるなど、保全上注目すべき鳥にもなっています。
名前の由来

ユニークな名前を持つハチクマだけに、その由来が気になりますよね。実は「ハチクマ」とは「蜂を食べるクマタカ(=クマタカというタカに似た鳥)」という意味から来ています。
ハチクマは外見がこのクマタカに似ていて、さらにハチ(蜂)を好んで食べる習性があるため、「蜂食(はちく)うクマタカ」→「ハチクマ」と名付けられたのです。

漢字では「蜂熊」と書くこともあり、一見するとクマの仲間のようですが実際はタカの一種。ややこしい名前ですが、名前に「クマ」が入っているのはクマタカ由来というわけですね。
ちなみにハチクマの英名は “Oriental Honey-buzzard”(オリエンタル・ハニーバザード)。直訳すると「東洋の蜂蜜ノスリ(※1)」という意味になりますが、実際には蜂蜜そのものを食べるわけではなく、後述するように蜂の幼虫やさなぎを主に食べます。
英名だけ聞くと「蜂蜜好きのトリ?」と思われるかもしれませんが、ハチクマが狙うのは蜂の子(幼虫)なのです。
※1.ノスリってどんな生き物?

タカやトビと言えば割とイメージしやすい生物ですが、「ノスリ」だとパッと思い浮かばない人もいらっしゃるでしょう。
ノスリは、全長55cm、ハシブトガラスと同じくらいの大きさのタカの一種です。(中略)主にネズミやモグラ、カエルなどを採食するため、それらの小動物の多い、農耕地、草原、河原などでよく見かけます。
三鷹市「ノスリ(鵟)ワシタカ科」
こちらは三鷹市ホームページからの引用ですが、ノスリについて写真と一緒にわかりやすく解説されています。また群れを形成せずに、単独もしくはペアで生活するのも彼らの特徴です。

ちなみに名前の由来は、「野を擦るように地面スレスレを飛行する」姿からきているという説が有力です。
>>「なぜスズメ?」を解決!スズメバチの名前の由来を種類別にまとめて解説
ハチクマの鳴き声
森林の上空を舞うハチクマですが、その鳴き声を耳にしたことはあるでしょうか。ハチクマはあまり鳴かない鳥と言われており、繁殖期などに出す声は限られています。
代表的な声は「ピューウ」という澄んだ響きで、トビ(鳶)が鳴く「ピィーヒョロロ」という声にどことなく似ています。ただしトビの声よりも短く、透き通った高めの音色で「ピーッ」と一鳴きする印象です。
私も山林での野鳥観察中にハチクマらしき猛禽を見かけたことがありますが、その時も羽ばたき音だけが聞こえ、声を発することはありませんでした。こうした静かな振る舞いも、森の中で密かに蜂の巣を探すハチクマならではの習性なのかもしれませんね。

上記のYouTube動画には、貴重なハチクマの鳴く声が収められています。気になるあなたは是非チェックしてみてくださいね。
刺されないのは羽根のおかげ?

ハチクマがスズメバチを主食にできる最大の理由が、彼らが持つ特殊な羽毛にあります。ハチクマの頭部から首・胸にかけては小さく硬い羽毛が鱗状に密生しており、まるで防護服のように体を覆っているのです。
この羽毛は非常に分厚く重なり合っているため、スズメバチが攻撃しても毒針が皮膚に届かず、ほとんど刺さることがありません。蜂の猛攻をものともせず巣を襲い破壊するハチクマの映像を見ると、その耐久力には本当に驚かされます。
さらに近年の研究では、ハチクマの羽毛にはスズメバチの攻撃性を弱める特殊な成分が含まれている可能性も指摘。ハチクマ自身が体から蜂用のフェロモンのような物質を発し、「自分は攻撃対象ではない」と蜂に認識させているのではないか、といった説もあるのです。
とはいえハチクマであれば、どんな状況でも絶対刺されないというわけではありません。興味深いことに、若いハチクマ(幼鳥)は顔まわりの羽毛が十分生え揃っていないため、スズメバチから刺されてしまうこともあるそうです。

猛毒針を持つスズメバチを相手に悠々と幼虫を奪うハチクマの姿は、まさに自然が生んだ不思議な適応戦略の結果なのでしょう。
>>毒針で攻撃してくるのはメスだけ?オスは噛むだけだから安全って本当なのか
蜂の巣を襲う理由

「なぜハチクマは危険を冒してまで、スズメバチの巣を襲うのか?」素朴な疑問ですよね。その答えは一言で言えば、巣の中にある「幼虫やさなぎ」を食べるためです。
スズメバチの幼虫(いわゆる蜂の子)やさなぎは高タンパクで栄養価が非常に高く、ビタミンやミネラル・必須アミノ酸なども豊富に含む貴重な栄養源。ハチクマにとってスズメバチの巣は、まるごと「栄養満点のご馳走」が詰まった宝庫と言えます。

特に日本に飛来するハチクマは5月に繁殖を開始し、9~10月には再び南方へ渡りを開始するため、わずか4~5か月の間にヒナを大きく育て上げる必要あり。この短い繁殖期間でヒナを無事巣立たせるには、高タンパクなエサで急速に成長させることが大切なんですね。
そこで目を付けたのが、スズメバチ類の幼虫やさなぎ。親鳥は森の中でスズメバチの巣を見つけると、鋭い鉤爪を持つ足で地中や樹上の巣を力強く掘り起こします。大量のスズメバチが巣を防衛しようと飛び回りますが、ハチクマはひるむことなく器用なくちばしを使い、巣板から丸々太った白い幼虫を次々と引き抜いていきます。
実は私もハチクマにあやかって(?)、貴重なスズメバチの幼虫を食べた経験あり。長野県のある道の駅で蜂の子の甘露煮が売られていたので興味本位で購入し、恐る恐る口にしてみました。すると予想に反してクリーミーでコクがあり、まるでナッツのような風味が広がったのです。

子供の頃から「蜂の子は栄養満点」と聞いていましたが、その旨みに驚きました。人間でも美味しく感じるくらいですから、ハチクマにとって幼虫やさなぎがご馳走なのも頷けます。栄養たっぷりの蜂の幼虫を頬張るハチクマの気持ちを、ほんの少しだけ実感できた気がしました。
>>スズメバチの幼虫は人間が食べても美味しいの?毒の有無から代表的な料理まで紹介
メスとオスの見分け方

ハチクマはオスとメスで、大きさや姿に若干の違いがあります。メスの方が全長で4cmほど大きいことはすでに触れましたが、外見上もっとも分かりやすい違いは目の虹彩の色です。
オス成鳥は虹彩が赤みがかった暗褐色をしていますが、メス成鳥の虹彩は明るい黄色。野鳥観察で双眼鏡越しにハチクマの目が確認できれば、その色で性別を判別できるほどはっきりした違いです。
総じてオスの方が精悍でメリハリのある色合い、メスは少し淡い色合いという違いがあります。以下にハチクマのオス・メスの主な違いを、表にまとめてみました。
| 特徴 | オス(♂) | メス(♀) |
| 体の大きさ(全長) | 約57cm | 約61cm |
| 虹彩の色 | 赤みがかった暗色 | 明るい黄色 |
| 尾羽の帯模様 | 太い帯が2本 | 細い帯が複数 |
| 顔つき・頭部の色 | 灰色がかった顔 | 茶褐色の顔 |
野外で双眼鏡を使ってじっくり見るなら、主な判別ポイントは上記の4つ。ただし個体差も大きく、一瞬で判別するのは難しい場合もあります。
実際ベテランのバードウォッチャーでも、ハチクマのメスと幼鳥を見間違えることがあるそう(幼鳥は虹彩が暗色でメス成鳥と紛らわしいため)。そのため確実に識別するには、虹彩の色に加えて羽の生え変わり具合(換羽の有無)など複数の特徴を総合的に見る必要があると指摘されています。

私自身、フィールドでハチクマらしき鳥を見ても性別までは判断できないことがほとんど。それでも図鑑や写真で改めて見ると、「なるほど、ここが違うのか!」と発見があり面白いですよ。
生息地や天敵なのに刺されないワケを理解したら|スズメバチを食べる鳥ハチクマを深掘り

- 飼育できる?
- 幼鳥の特徴
- ハチクマにも天敵はいる?
- 絶滅危惧種なのか
- クマタカとの見分け方
- カラスもスズメバチの天敵?
飼育できる?

結論から言えば、野生のハチクマを個人が飼育することはできません。ハチクマは日本の法律で保護されている野鳥であり、許可なく捕獲・飼養することは禁止されています。
「スズメバチの天敵だから、飼っておけば害虫駆除になるのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、現実的ではないでしょう。まず猛禽類の飼育には専門的な設備と餌・知識が必須で、一般家庭でスズメバチを食べさせながら飼うのは不可能に近い話です。
さらには前述のとおり法律違反の問題も。同様によく名前が挙がるクマやニワトリ(野生)・カラスなど他のスズメバチの天敵についても、ペットとして蜂の巣駆除に使うのは非現実的ですよね。

スズメバチ対策は専門の業者や適切な駆除方法に任せ、ハチクマは野生のままそっと見守るのが一番と言えるでしょう。
幼鳥の特徴

ハチクマの幼鳥(ヒナや巣立ち直後の若鳥)は、成鳥とはまた異なる特徴を持っています。まず繁殖スケジュールの項でも触れたように、ハチクマのヒナは驚くべきスピードで成長します。
外見面では、幼鳥は全体的に成鳥よりも淡い色合いであることが多く、羽の模様も多少異なります(※ハチクマは個体差が大きいため一概には言えませんが、クマタカの幼鳥が白っぽい羽毛をしているのと同様、ハチクマ幼鳥もやや淡色の傾向があります)。
また幼鳥は虹彩(目の色)が暗褐色~黒に近く、成鳥メスの黄色い虹彩とは明確に異なるため、近くで見れば年齢を判別する手がかりになります。嘴(クチバシ)の付け根にある蝋膜(ろうまく)の色も幼鳥は異なり、こうした点で経験者は見分けているようです。

なお生後4~5年ほどかけて、成鳥と同じ羽の色柄に換わっていくと考えられています。幼鳥から成鳥になるにつれ顔つきも精悍さが増し、蜂を食べるタカとしての風格が備わっていくのでしょう。
興味深いことに、幼鳥の間はスズメバチに対する耐性も不完全。若い個体は顔周りの防御羽毛が未発達なため、巣を襲った際にスズメバチに刺されてしまうケースもあると報告されています。親鳥ほどの完全無敵ぶりは、幼いうちはまだ発揮できないのですね。
ハチクマにも天敵はいる?

ハチクマはスズメバチにとっての天敵ですが、ではハチクマ自身に天敵はいるのでしょうか?結論として、成鳥のハチクマにはこれといった天敵はほとんどいないとされています。
生態系においてハチクマは上位捕食者のポジションにあり、自らが狙われる場面は多くありません。オオタカやクマタカなど他の大型猛禽類と遭遇しても、空中では互いに牽制し合う程度で直接捕食されるケースは稀でしょう。

強いて挙げれば、ハチクマの卵や雛はカラスやヘビ類に狙われる可能性あり。親鳥が留守中に樹上の巣がカラスに荒らされ、卵が食べられてしまった例などは他の鳥類でも知られており、ハチクマでも油断はできません。
もっともハチクマは繁殖期に番(つがい)で協力して巣を守るため、自然界での天敵による被害はごく限られていると考えられます。
その結果ハチクマは個体数が徐々に減少傾向にあり、保護が必要な状況になりつつあります。このようにハチクマは天敵が少ないが環境に弱い鳥。生態系の頂点に立つ猛禽類ほど環境変化の影響を受けやすい傾向がありますので、ハチクマも例外ではないのでしょう。
絶滅危惧種なのか

ハチクマは現在、国際的には絶滅危惧種とはされていません。IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストでは低リスク(Least Concern, LC)に分類されており、世界的な個体数は比較的安定していると見られています。
各都道府県のレッドデータブックでも、ハチクマは希少種として掲載されている場合があります。例えば青森県や長野県・京都府などでは、繁殖数が減少していることから絶滅危惧II類相当と評価されています(地域によってカテゴリーは異なります)。
またハチクマは渡り鳥であるため、日本国内だけで保全策を講じても十分でない可能性あり。繁殖地の森林保護はもちろん、渡り中継地や越冬地での狩猟圧や森林伐採の抑制など、国際的な協力も重要になるでしょう。

幸いハチクマはその生態の特異さから研究・保護対象として関心が高まっており、各地の野鳥保護団体や研究機関がモニタリングを続けています。私もハチクマの動向には注目しており、美しいこの猛禽が末永く空を舞えるよう願っています。
クマタカとの見分け方

ハチクマとよく比較される鳥に、クマタカ(クマタカ科の大型猛禽)があります。名前も似ており生息環境も重なるため混同されがちですが、両者は全く別種のタカ。ここではハチクマとクマタカの違いを整理し、フィールドでの見分け方を解説します。
まずサイズですが、クマタカはハチクマより一回り以上大きいです。ハチクマが全長60cm前後(オス57cm・メス61cm)なのに対し、クマタカはオス約75cm・メスは80cmにも達します。
翼を広げた翼開長(よくかいちょう)もハチクマの約135cmに対し、クマタカは160~170cmと非常に幅広い翼を持っています。飛翔時に見比べると、クマタカの方が翼が太く長くがっしりしており、遠目にも大型であることがわかります。
次に外見上の特徴ですが、最大の違いはクマタカの頭にある白い冠羽(かんむりばね)です。クマタカは後頭部に白く長い羽根束が立っており、横から見ると角のように突き出して見えます(漢字名「角鷹」はここに由来します)。

一方でハチクマにはそのような冠羽がなく、頭は滑らかなシルエット。したがってもし頭に羽根の冠が見えればクマタカ、なければハチクマと判断できるでしょう。
羽の模様にも顕著な差があります。ハチクマの腹部は淡褐色~白茶色の地に黒っぽい横縞がある程度ですが、クマタカの腹部は白地に太い黒褐色の帯模様がくっきり入ります。
クマタカは全体に白と黒のコントラストが強く、特にお腹から脚にかけての羽毛は白地に黒い横斑がはっきりしています。翼の下面にも濃淡くっきりした帯模様が走り、尾羽にも数本の太い帯があります。
ハチクマは個体によっては腹が白っぽいものもいますが、多くは淡い茶色でここまで明瞭な白黒模様はありません。飛翔中に下面が真っ白に見えて模様がクッキリしていればクマタカ、薄茶色~淡い色合いで模様がぼんやりならハチクマの可能性が高いです。
さらに餌の面ではハチクマが主にハチ類(他にカエルやヘビ、小型鳥類なども)を捕食するのに対し、クマタカはウサギやリス・キジなど小~中型の哺乳類・鳥類を幅広く捕らえます。ハチクマが蜂の巣を狙うのに対し、クマタカは森林内でリスや野鳥を狙う、とエサからして異なるのです。※2
以上のポイントを簡単に表でまとめます。
| 識別ポイント | ハチクマ | クマタカ |
| 大きさ (全長) | 約57~61cm(トビ大) | 約75~80cm(かなり大型) |
| 冠羽の有無 | なし | あり(白い長い冠羽) |
| 胸~腹の羽模様 | 淡褐色地に細い横縞(個体差大) | 白地に太い黒帯模様 |
| 日本での季節 | 夏鳥(5~9月ごろ滞在) | 留鳥(一年中生息) |
| 主な食性 | スズメバチなど昆虫、両生類 etc | 小型哺乳類(ウサギ等)、鳥類、爬虫類 etc |
ご覧のように、見分けるポイントはいくつかあります。特に冠羽の存在と体の模様はフィールド識別の大きな手がかり。私も最初にクマタカの写真を見たとき、その白い冠羽の凛々しさに「ハチクマとは全然違う!」と感動したものです。
またクマタカはその大きさと勇猛さから、「森の王者」とも称される存在。一方のハチクマは地味ながらも、蜂を主食にする異色のタカとして光るものを持っています。

同じタカ科でも、これほど生態が違う二種がいることは興味深いですね。ハチクマとクマタカ、出会った時には是非この違いに注目して観察してみてください。
※2.クマタカはムササビやカラスも食べる?
クマタカの食性はかなり多様で、上記で説明した動物以外にも様々な生き物を捕食します。
餌の種類は多く、森林に生息するさまざまな中小動物であるが、ノウサギ、キジ類(キジ、ヤマドリ)、ヘビ類(アオダイショウ、ヤマカガシ等)の3グループが大半を占める。他に、哺乳類ではモモンガ、ムササビ、アナグマ、リス、テン、イタチ、ネズミ類、ヒミズ類、キツネ・タヌキの幼獣等、鳥類ではライチョウ、コジュケイ、カケス、カラス類、ヒヨドリ、キジバト、アオバト等と多様である。
環境省「クマタカの概要」
愛らしい見た目のモモンガがいたり、猛毒を持つ危険な蛇ヤマカガシがいたりと実に多彩なラインナップ。ちなみにあまり聞き慣れない「ヒミズ」は、モグラに似た小型の哺乳類です。


漫画および映画「ヒミズ」ファンのあなたは、既にご存知だったかもしれませんね。
カラスもスズメバチの天敵?

スズメバチを食べる生き物として、カラスを思い浮かべる方もいるかもしれません。確かにカラスは雑食性が強く、昆虫から果実・人間の出すゴミまで何でも食べる賢い鳥です。
スズメバチもカラスの餌範囲には含まれており、実際に飛んでいるスズメバチを捕まえて食べてしまうカラスの動画も報告されています。特にハシブトガラスやハシボソガラスは都市部にも多く、生ゴミに混じった蜂の死骸などをついばむ姿も見られます。
しかしカラスは非常に知能が高いため、危険の伴うスズメバチを積極的に狙うことは稀。わざわざ刺されるリスクを冒さなくても、カラスには他に安全で栄養豊富な餌が数多くあるからです。例えば畑の残渣や人間の出す食品ゴミ・小動物の死骸など、スズメバチより手軽に手に入る食べ物を優先するでしょう。

私の知人が養蜂箱を荒らすスズメバチ対策に、「蜂の天敵の鳥を放せばいいのでは」と冗談半分に言っていましたが・・・カラスに頼るのは現実的ではありません。カラス自身がスズメバチを怖れているわけではないでしょうが、「割に合わない」と本能的に理解しているのでしょうね。
つまりカラスも広い意味ではスズメバチの天敵(捕食者)になり得ますが、それはイレギュラーなケースに限られます。スズメバチ側から見ても、クマやハチクマほど脅威となる存在ではありません。むしろカラスにとってスズメバチは自分が刺される危険がある厄介な相手で、必要以上には関わらないのです。
以上、スズメバチを食べる鳥「ハチクマ」について、その生態や特徴を幅広く深掘りしてみました。人間にとって恐ろしい存在のスズメバチを平然と食べてしまうハチクマは、知れば知るほど不思議で魅力的な鳥。生息地から習性・他の猛禽類との比較まで、本記事がお役に立てば幸いです。
まとめ:ハチクマはスズメバチを食べるけど刺されない鳥|天敵の生息地~見分け方を総括

- ハチクマはタカ科に属する大型の猛禽。翼を広げると約135cmにもなる
- 日本では夏鳥として渡来し繁殖、秋には東南アジア方面へ渡る渡り鳥
- 名前の由来は蜂を食べるクマタカに似た鳥。「蜂食うクマタカ」→「ハチクマ」
- スズメバチを食べても刺されないのは首まわりにある硬く密集した羽毛のおかげ
- 羽にスズメバチの攻撃性を抑える成分が含まれる可能性が議論・研究されている
- スズメバチの巣を襲う理由は幼虫やさなぎを食べて高タンパクな栄養を得るため
- ハチクマのメスはオスよりやや大きく、目の色が黄色い点で見分けられる
- 幼鳥は羽毛や防御力が未発達で、成鳥に比べスズメバチに刺されやすい
- 成鳥のハチクマに天敵はほぼ無し。卵・ヒナはカラスやヘビに狙われることも
- 日本では環境省のレッドリストで「準絶滅危惧種」に指定。保護の必要がある
- クマタカとの違いは、冠羽の有無や体の大きさ・模様・食性などで見分ける
- カラスもまれにスズメバチを食べるが、ハチクマほど積極的な天敵ではない
- ハチクマは飼育が法律で禁止されており、自然の中で観察するにとどめるべき
- 生態系の頂点に立ちながらも環境変化に弱く、人間活動が最大の脅威
- スズメバチを恐れず攻撃する森のハンター。自然の不思議さを感じさせる存在
機会があればあなたもぜひ初夏から秋にかけて里山を訪れ、天空を舞うハチクマの勇姿を探してみてください。きっとその姿に感動するとともに、「蜂を食べるタカ」というロマンあふれる生態に思いを馳せることでしょう。

ハチクマの大胆さと自然の巧みな仕組みには、私もすっかり心を奪われてしまいました。